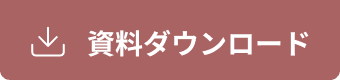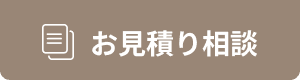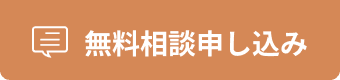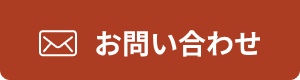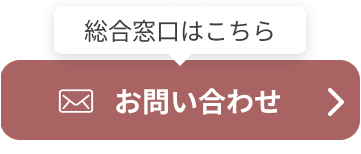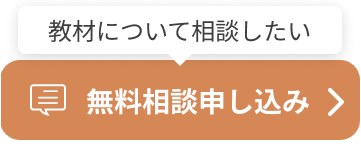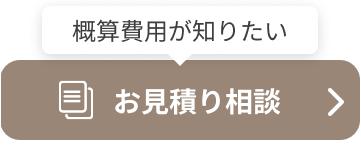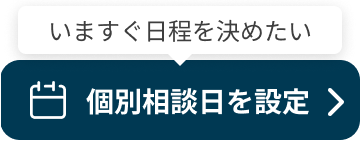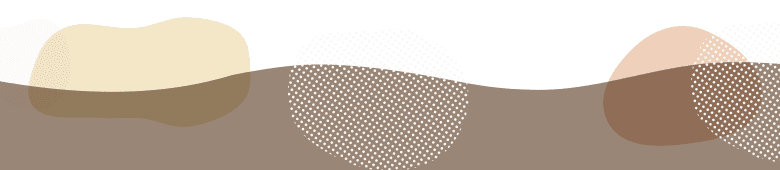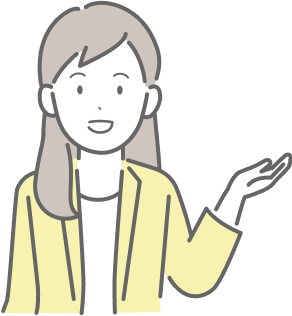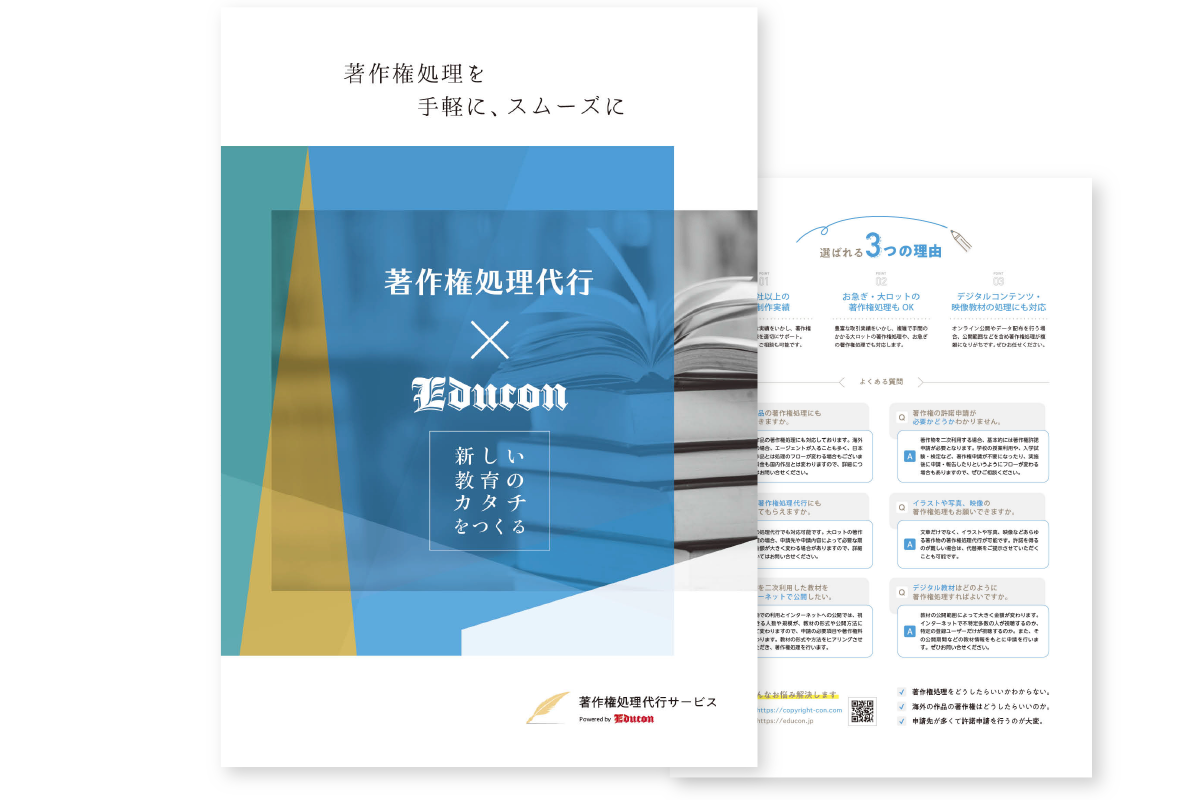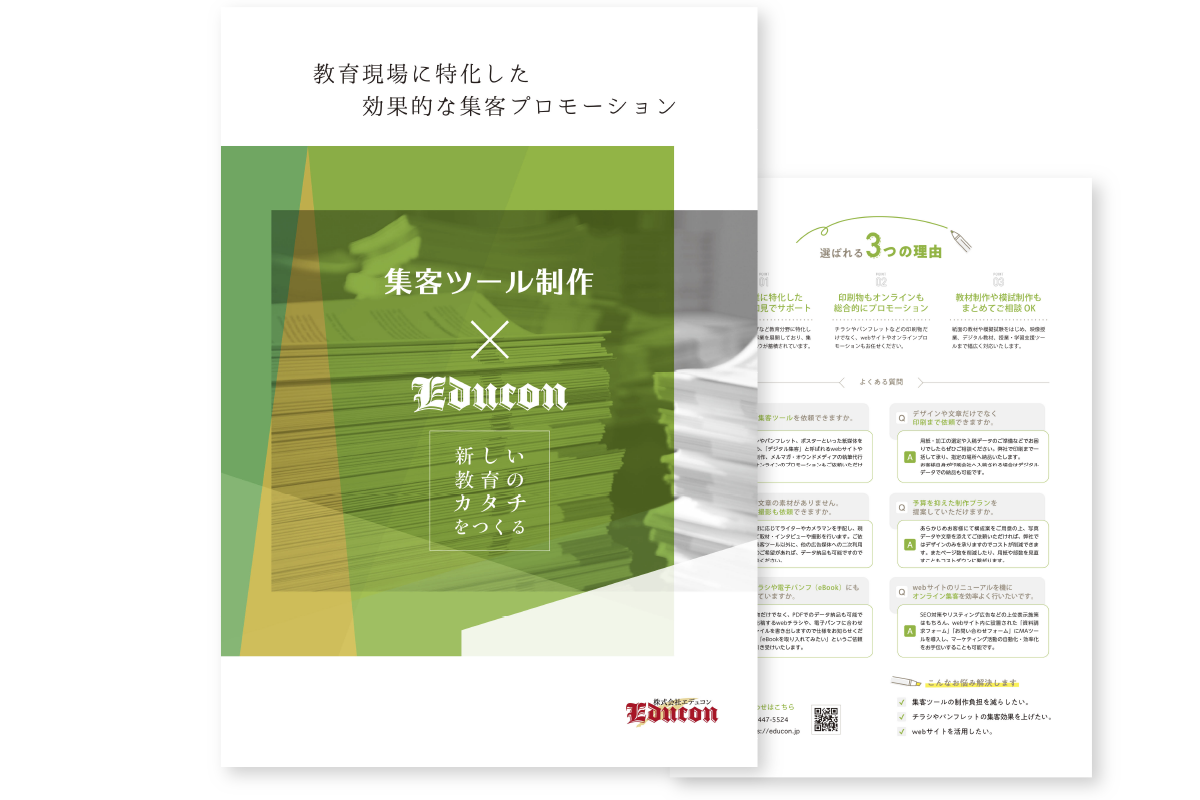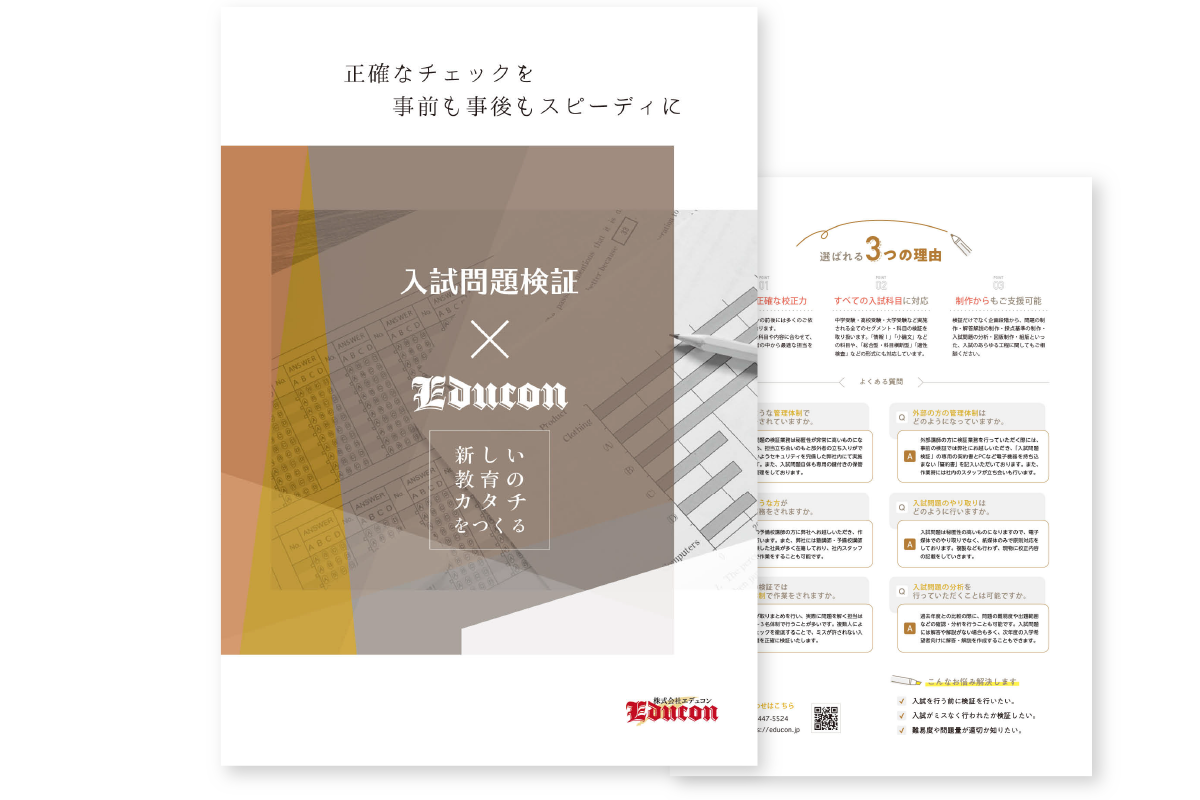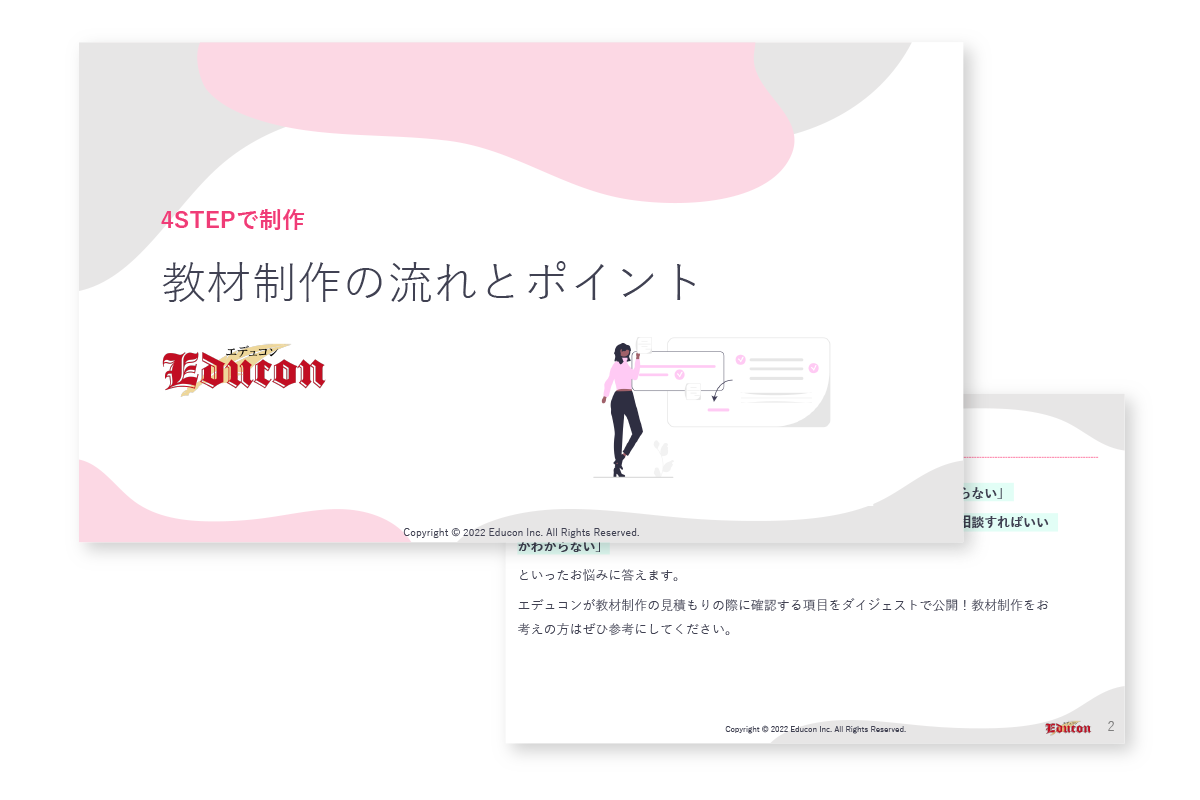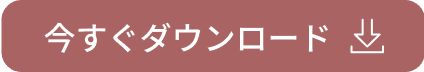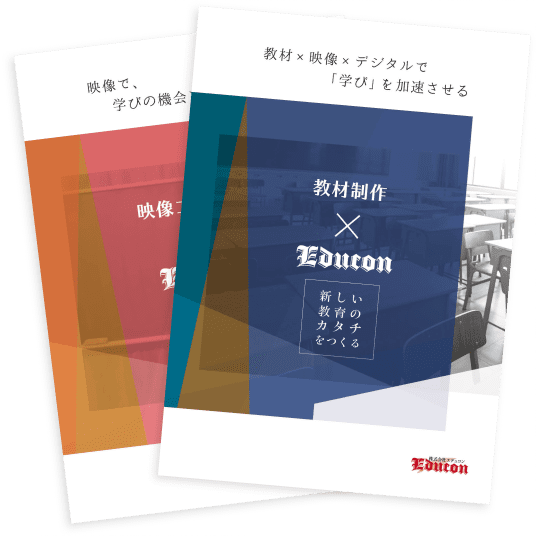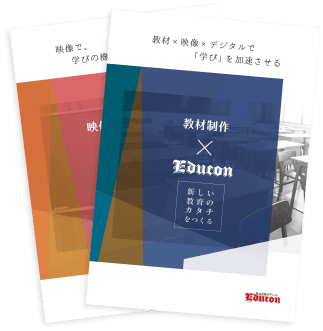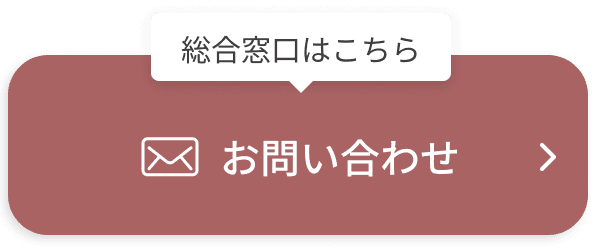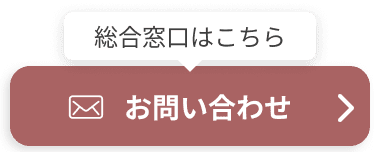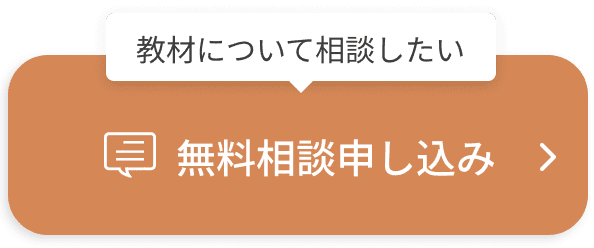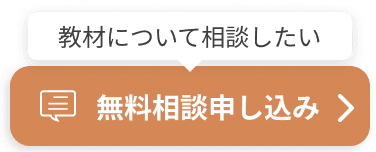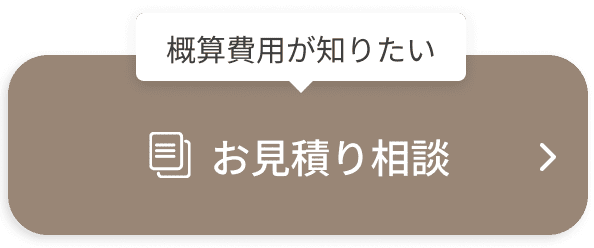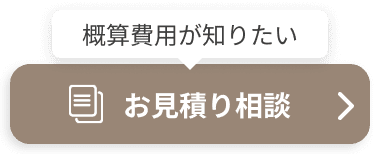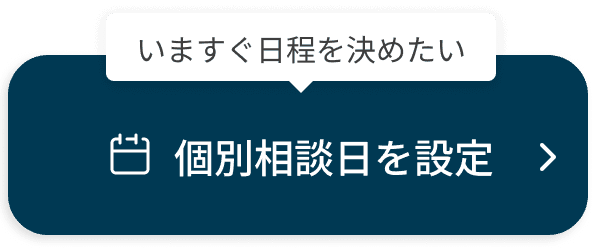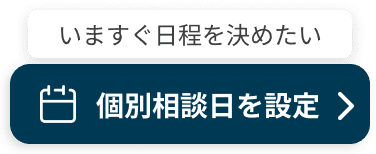コラム
校正と校閲の違いって!?
カテゴリ

最近はドラマでも取り上げられ、一般の方にも広く知られるようになった「校閲」。それとよく似た言葉で「校正」という言葉があります。「校正」と「校閲」は出版社や新聞社、その他印刷会社などで昔から行われてきた、公に文章を発信する企業には欠かせないプロセスです。言葉としては耳にすることもありますが、実際の違いを説明できる方は少ないのではないでしょうか。 今回は「校正」と「校閲」がどのようなものか、両者のどこが違うのかなどを解説します。
校正・校閲とはどのようなものか
広辞苑によると、校正とは「①文字の誤りをくらべ正すこと。②校正刷を原稿と引き合わせて、文字の誤りや不備を調べ正すこと。」と記されています。具体的には、文章の中の誤字脱字や日本語の言い回し、原稿と校正刷を比べて相違点がないかなど、その書かれている「言葉」の誤りを正すプロセスであると言えます。 一方の校閲とは「しらべ見ること。文書・原稿などに目をとおして正誤・適否を確かめること。」と記されています。具体的には、文書や原稿などに書かれた内容が事実と異なっていないか、言葉や文章の内容につき整合性が取れているか、取れていない場合は訂正する、つまり言葉が指している「意味」や「内容」を正すというプロセスです。 どちらも文章内の誤りを見つけ、それを正すプロセスであり、どちらも文章作成において欠かせない行程ではありますが、それぞれチェックする内容が異なります。校正は「言葉」自体を、校閲は「言葉が指す意味」を見る仕事なのです。 どちらも高いスキルや知識が求められる仕事であり、大手の出版社、新聞社、印刷会社には専門の部署が置かれているほどです。校正校閲はとても難易度が高く、重要な仕事であり、校正校閲専門の部署の担当者はいわば「日本語のスペシャリスト」なのです。
なぜ校正校閲が必要か
では、校正や校閲はどうして必要なのでしょうか。 ・読み手の負担を減らす、読み手に不利益を与えない ・文書の説得力、発信者の信頼性の担保 ・著者や編集者の成果物をさらにブラッシュアップする ・文章が世に出るまでの「最後の門番」的な存在 当然のことながら、書かれていることが正しいかどうかわからない場合、読み手はそこに書かれていることが事実かどうかを調べる手間が必要となり、読み手が安心して文章を読むことができなくなります。 また公に発する文章が間違っていたとあれば、その企業の責任や信用に関わる問題となります。場合によっては損害賠償責任を負うような事態にもつながりかねません。そこで必要となってくるのが、「校正」「校閲」なのです。こういった問題は、出版社や新聞社などだけでなく、公に何かを発信するどのような企業にも関係しています。
具体的なチェック方法
実際に校正校閲はどんなことを行うのでしょうか。校正校閲の担当者はただ文章を読むだけではなく、以下のようなポイントを中心にチェックをしながら、文章に目を通していきます。 「校正」では以下のようなポイントをチェックします。 ・誤字脱字がないか ・文章の一貫性 ・「ですます調」か「だ・である調」か ・数字単位や英字の表記統一 ・固有名詞に間違いがないか 人が作成している文章である以上、どんなに気をつけても誤字脱字は出てくるものです。これらをチェックするのが校正の一番の仕事。同音異義語や送り仮名や固有名詞に間違いがないかなどが主なチェック項目です。 また、数字や英字、記号の半角全角などの表記のルールや文章表現などに一貫性があるかなども挙げられます。文章に一貫性がないと非常に読みにくい文章になってしまいます。こういった箇所も校正でチェックしていきます。 「校閲」では以下のようなポイントをチェックします。 ・事実と相違していないか ・数値やデータに誤りがないか ・表記のゆれなど ・文章表現の誤りがないか ・著作権や引用などにも注意する必要がある。 記された内容が事実と異なっていては、読者が困惑すると共に、発信者の信頼問題、な用によっては訴訟問題にも発展しかねません。 また、不自然な日本語、接続詞、修飾語の使い方、使用している言葉の意味、言葉の「係りと受け」がきちんと機能しているかなど日本語的な表現が間違っていないかなどもチェックしています。 上記に挙げたのはほんの一例に過ぎず、校正校閲では様々な観点から文章をチェックしています。
校正校閲を怠るとどのようなトラブルが起こるのか
万が一校正や校閲がうまく機能せず、チェックをすり抜けてしまい、そのまま間違った情報を開示してしまった場合には、様々なトラブルにつながる可能性があります。特に最近ではインターネットの普及で情報が拡散するスピードは早く、ちょっとした誤りが取り返しのつかないようなトラブルにもつながりかねません。 例えば、校正の段階で人名の誤りを訂正できなかった場合、すでに発行してしまった書物を訂正、回収することになれば膨大なコストがかかってしまうことがあります。 メーカーの商品カタログにおいては、販売価格の桁数が間違っていた場合には、想定よりも安い金額で販売されてしまい、赤字になってしまったり、商品の性能に関する記載に誤りがあった場合などはカタログの回収のみならず、そのことが理由で事故が起こった場合などは損害賠償を請求されるような事態にも繋がりかねません。 例え誤りが小さなものであったとしても、大きな損害や信用喪失などの問題に発展しかねないのです。
校正校閲に必要な知識、スキル
今まで見てきたように、校正校閲はとても重要かつ項目は多岐にわたり、専門性の高いプロセスであることがわかりました。 校正校閲には言葉や文章構成などの日本語に関する知識についてはもちろん、専門用語、専門知識、物事の背景や因果関係など、幅広い知識が必要になります。このため、校正校閲を行う者は、その道のプロフェッショナルであることが望ましい。 これを自前でやろうとすると、書物やインターネットその他のツールを駆使して、様々な調査をする必要があり、膨大な時間を費やすことになります。 また、これらの誤りを見つけるには、情報が信頼できるものであるかどうかを見極める力が必要になります。こういった力は一朝一夕では会得することはできず、長い間の経験や蓄積が必要になります。 このような問題をクリアするため、現在では校正校閲に関する有料無料の様々なソフトなど便利なツールもあります。また、校正校閲を専門の業者に外注する企業も増えています。専門知識を持ったプロフェッショナルに任せてしまえば安心です。 これらのツールや会社を利用し、校正校閲に万全の体制を整えることで、クオリティの高いコンテンツ制作に努めることは、企業価値を高めることにもつながるのです。
株式会社エデュコン
【総合パンフレット】のご案内
デジタル教育コンテンツの市場拡大における取り組みや、エデュコンのビジネスモデル・事業領域などをまとめたパンフレットをダウンロードいただけます。
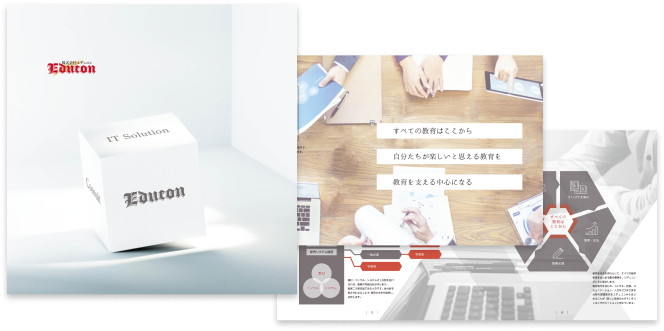
株式会社エデュコン 総合パンフレットのご案内
デジタル教育コンテンツの市場拡大における取り組みや、エデュコンのビジネスモデル・事業領域などをまとめたパンフレットをダウンロードいただけます。